SOUNDRADIX ARTIST - ENA - PAGE.2
前回の記事ではSoundRadix Surfer EQを中心にお話をお伺いしましたが、今回はENA氏自身の音楽制作のお話を少しお伺いする事が出来ましたので、そちらを中心に。
なお、近くENA氏待望の2作目のアルバム「Binaural」がリリースされます。リリースは「Samurai Horo」という海外のレーベルですが、日本国内の流通も開始するとの事ですので、是非とも手に取って、リアルに世界を股にかけるENA氏の音を体験してみてください。
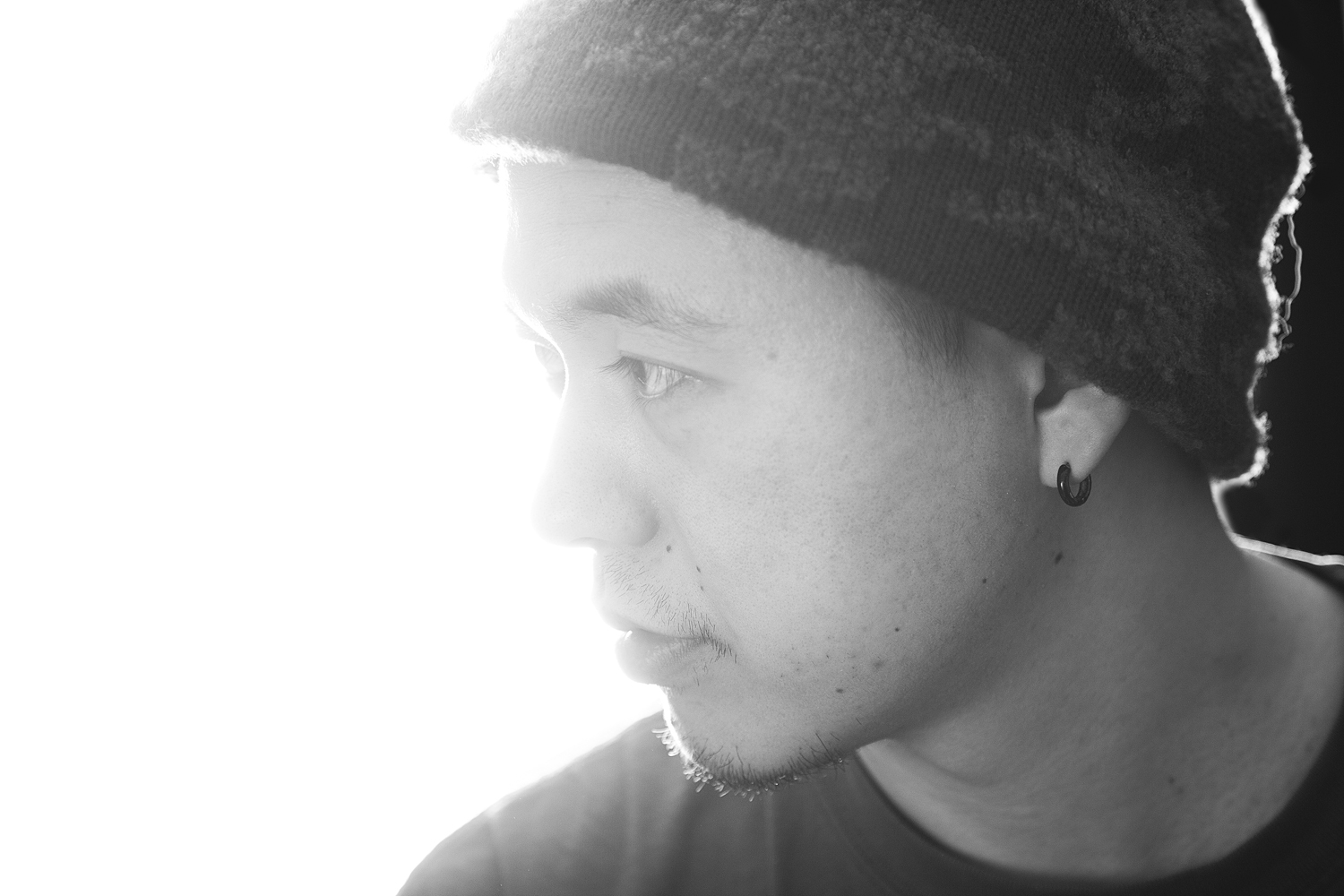
ENA(7even/Samurai Horo)
Drum&Bassから派生した独自な音楽の評価が高く、Loxy、Surgeon、Mu-Ziq、Peverelist、Pangaea、Laurent Garnierなど、ジャンルを問わないTopDJからのサポートを受け、Resident AdvisorのPodcastに自身の曲を中心としたMixを提供。多数のレーベルからリリースを重ねると同時に、楽曲のクオリティの高さからミキシング/マスタリングの評価も高く、様々な作品にエンジニアリングでも参加。2013年には7even Recordingsからアルバム"BILATERAL"をリリースし、日本全国、アジア、ヨーロッパとツアーを成功させると共に、今最も注目されているレーベル"Samurai Horo"のコンピレーション作品"Scope"に2曲提供。2014年3月には"Bacterium EP"を同レーベルから発表し、10月にはヨーロッパツアーと共に2ndアルバム"Binaural"がリリースされる。
more info : http://flavors.me/ena_
9割位はオーディオ、去年のアルバム「Bilateral」もそうだった
そうですね。MIDI ノート機能はオーディオにとって色んな可能性をもたらすんじゃ無いかと思います。ところで、その「オーディオを使う」という事の利点というのはどこにあるのでしょう?例えば、そんな事しなくてもシンセで打ち込めば良いじゃないか、と考える事も出来ると思うのですが。
シンセでMIDI とオートメーションを使えば、一緒と言えば一緒ですが、個人的にはオーディオである方がダイレクトに音を変えられるからでしょうか。例えばグルーブを作る時ってアタックからリリースしきるまでの具合がとても重要で、それをシンセだったりドラムマシンでやろうと思うと一音一音に対してエンベロープを書かないと中々思う音になってくれない。
でもオーディオならサンプルクリップごとに長さもフェードもフェードカーブもダイレクトに触れるし、音のイメージを具体化するのがシンプルでダイレクトなんですよね。
確かにオーディオの方が音楽的には断然直感的ですよね。シンセは更にもう一歩を詰めるとなると結構時間がかかってしまう印象があります。
それに、今のDAWはオーディオであってもピッチとかタイムストレッチとか結構自由に色んな事が出来る。
なるほど。一音一音にこだわりを、という部分は手軽にソフトシンセを買ってループして、って事で完結しがちな現代人と、世界的に評価されるENA さんとの具体的な違いを垣間見た気がします。という事は普段から制作ではオーディオベースなのですか?
9割位はオーディオで作ってると思います。少しはソフトシンセを使う事もあるけども。去年のアルバム「Bilateral」もそうだったし、次のアルバム「Binaural」も殆どオーディオですね。 とにかくオーディオを壊して、壊して、壊してって自分の音を作ってます。
本当に個性的ですものね(笑) では、このままENA さんの「音作りの観点」みたいな所についてもお伺いしたいと思います。 ENA さんは、第三者から見た場合、少なからずベースミュージックのプロデューサーであると捉えられている事が多いと思います。 加えて、音作りやエンジニアリングの面においても高く評価されていると思います。そんなベースミュージックの枠組みの中で評価を得るENA さんが、「ベース」というものを作るときに、特に注意しているポイントみたいなのをお伺いできますでしょうか? もちろん、気をつけている事なんてケースバイケースで山ほどあるとは思うのですが、多くのプロデューサー達は「どうやったら、こんなにしっかり鳴るベースが作れるんだろう?」って思っていると思います。 また、ENA さん自身が、そうしたアーティスト達のダブ(デモ)を耳にしたときに、「ここが足りないな。」と感じられる事もあるかと思います。そうした意味で、特に重要に感じられている事というのは、どういう部分だと思いますか?
やっぱり色々あるんですけど、特には低域のレンジ(帯域)ですかね。
重いベースを出したい、って事で単純にキーを下げると再生環境によっては聴こえない帯域しか出てないって事になりがちで。
でも「ラインをはっきりさせる」というような作業を一つ通過する事で、鳴りが良くなる事が多い。
ただ帯域も重要ですが、基本的には鳴り易いフレーズが生きる曲を作る事が重要だと思います。極論を言えば鳴るアレンジ、曲の組み方をすればミキシングとマスタリングは必要無い位に思っています。
という事は、制作段階からベースの音階が再生環境に左右されにくい音程を使う、という事をある程度は意識している、という事もありますか?
ある程度は、ですけどね。
そもそも低音がちゃんと鳴るって事は基本的な事だと思うので、一番重要なのは音楽がちゃんと成立してる事ですからね。
メロディアスな曲が好きならメロディで聴かせられる様に作り込むとか、ビート主体であれば、ドラム一つ一つの音色をしっかり作って飽きさせない作りができているだとか、そうしたところが一番重要だと思います。
海外は一般的に、日本のサウンドシステムに比べて低域が出る場合が多い
なるほど。出演される場所の音響によって音楽の表情は変わってしまうけども、どこに行っても、それはそれで面白みがなくなる訳じゃない音楽を作ろう、という事ですね。 ところで、ENA さんは海外ツアーを毎年こなしていらっしゃいますが、実際、海外と日本の音響というのにはどういう違いがあると思いますか?個人的にはBack to Chill はしっかり低域が出ている印象をもっていますが、そうした環境って日本では数えるほどしか無く、対して小規模な場所では騒音問題の影響などもあって60Hz 以下を切る設定である事も少なく無いですし、何となく「海外の方が音が良い、日本はダメだ」みたいな雰囲気を感じる事があります。
確かに海外は一般的に、日本のサウンドシステムに比べて低域が出る場合が多いんですが、ただとりあえず出るって感じが多くて、場所によってはだらしなく全部出る事も結構あります。だから「日本の方が良い」とか「海外の方が良い」って事はあんまり無いんじゃないですかね?国内でも海外でも良い所は良いですからね。
低域が出るけど音響が整ってない、というのは何だかとても大変そうですね(笑) でも、日本では海外に比べ低域が出ないとすると、サブベース(超低域)に関して、どれだけ出ているのか?という事を体感できる機会が少ないのでは?とは思う事があります。また、個人的にはサブベースは家庭用スピーカーとかヘッドフォンでは正確に捉えがたいものだと思うのですが。
ヘッドフォンは、本当より低域が出ているように聴こえがちですからね。モニターはそれなりのものを買って、ちゃんと設置も気をつかえば、ある程度までは詰められると思います。ただ、やっぱりサブベースは独特で経験で詰めてく部分は大きいと思います。音を作ってみて、現場で出して、持ち帰ってエディットして、また現場で出して…ってトライ&エラーを繰り返してくなかで、段々ちょうど良いところが分かってくる。
なるほど。出るにしろ出ないにしろ、結局はそれをどう捉えて「ちょうど良いところ」に出来るかが鍵なので、日本だからと悲観的になる必要はない、という事ですね。個人的な音楽に対してのお考えまでお答え下さって有り難うございます。
SURFER EQ の青のバンドが8dbも上がってて。でも普通に良い具合
では、最後に。ENA さんが今回SURFER EQ を使ってみて、一般の方にとって「こんな使い方良くない?」みたいな使い道がありましたら教えてください。
最初の方でも話した「ツール的EQは慣れが必要」というような事があって、実際、初心者とかだと上手く調整をするのって中々難しいと思うんですよね。変なピークについても、見逃したりとか、逆に意図せず作ってしまうって事も多いと思うし。
そういう意味ではSURFER EQだとSURF ボタンを押して、音楽的な感覚で何となく触れば変なピークが出来難く音質補正が出来る、という事があると思うんですよね。あまり考えずに、とにかくSURF ボタンを押せ!的な。
それは確かに良い使い道ですね(笑)普通のEQ だと厳密な作業が必要になるし、時間経過(音程が変わっていく)の事も考えると、便利ですものね。
例えば、歌モノのボーカルミックスって、A メロ→B メロ→サビって流
れに連れて音程だったり歌い方が変わる事が多いので、3つくらいのトラックに分けて作業する事が多くて。
それをSURFER EQ だと、上手く行けばワントラックで完結させる事が出来たり。実際ボーカルミックスで使ってみたんですけど、その時は上手く出来たので難しい事を考えないで簡単に使ってもナチュラルな音なんだって思いました。
その時はボーカルレコーディングの音質のせいでもあったんですけど、SURFER EQ の青のバンドが8dbも上がってて。でも普通に良い具合には調整できていたんですよ。フレーズによってというのはありますが、ツール的EQで8db上げたら、硬くなり過ぎててしまうケースが多いんですよね。
EQゲインが8db っていうのは、かなり大きいですよね。
それだけ好きなように触れる余地があるって事だと思うんです。
取りあえずSURFボタンを押して、Q とゲインを上げたり下げたりしてれば、自然といい感じの音が見つかり易い。
例えば右から順番に、ピンクのバンドが「Bright」、青が「Tight」、黄色が「Fat」、赤が「Heavy」みたいな捉え方とか、本当にシンプルに使えば良いと思いました。
そういう使い方が可能なくらい、SURFER EQ はある程度いい感じに仕上げてくれる節はありますものね。
むしろプロでやっている人の方が「簡単・スピーディ」である事が重要条件ではあるんですよね。品質が良いって事は間違いなく必要ですけど、使い勝手の悪い機材は中々定着しづらい。
SURFER EQ は今のままでも十分簡単だと思いますけど、それこそプリセットで楽器別に対してのセッティングを用意するとか、いっその事Vocal用だったり、Bass用だったりでパラメータの数とかを最適化して別のプラグインとして分けてしまうとか。
SURFER EQ は、そうやってどんどん今までの周波数固定EQとは違う次元のイコライジングを可能にしていける品質の高さとポテンシャルがあると感じますね。
戻る
written by toshiyuki kitazono.



